SV-BONYさんからお借りしている「SV230スーパーズームを試す」の最終回です。
かなり昔の話になりますが、1969年アポロ11号が月面着陸に成功し、翌1970年大阪で開催された万国博覧会の目玉としてアメリカ館に「月の石」が展示されました。当時小学生の私は家族で万博に出かけたわけですが、目当てのアメリカ館は最後尾がどこかわからないほどの大行列で結局「月の石」を見ることはできませんでした。それが悔しくて仕方がなかった私は天体望遠鏡で月を見れば小さな石ころより凄いものが見えるはず~と思い、お年玉とおこづかいを貯めてカートンの6㎝屈折経緯台を手に入れたのでした。その6㎝の天体望遠鏡で見た月は想像をはるかに超えるもので、一気に星の世界へズブズブと嵌っていきました。
その時の6㎝屈折は焦点距離が1000㎜で付属していたアイピースがH-8㎜、H-12.5㎜、H-20㎜でした。きっとこの時に付属していた3本の小さなツァイスサイズアイピースが初めて天体望遠鏡を手に入れたTaizo少年の心をガッチリつかんだものと思います。
今考えても望遠鏡の焦点距離にもよりますが、1000㎜前後の焦点距離であればやはり初心者には8㎜(125倍)~20㎜(50倍)くらいが扱いやすいアイピースだと思います。
そんな経緯から今回のこの8㎜~20㎜のズームが初心者ならずとも使い勝手の良いレンジを押さえた「神アイピース」になるかも~と思った次第です。
半世紀も前の当時は初心者用の天体望遠鏡は6㎝屈折望遠鏡または10㎝反射望遠鏡が一般的でしたが、現在であれば私は下記のような10㎝クラスの屈折望遠鏡が一番使いやすいものなのかと思います。

この望遠鏡はSV-BONYさんのSV503 102ED (口径102㎜ F7)で私はちょい見用として、ZERO経緯台に乗せて使っています。
ZERO経緯台は現在は販売はされていませんが、同様の経緯台がSV-BONYさんからSV225経緯台として販売されています。
今回はこの組み合わせで月を眺めてみようと思います。
SV230スーパーズームはアメリカンサイズの天頂プリズムでも使えますが、バランスが良くないので私は2インチスリーブを付けて2インチの天頂ミラーを使います(ギリギリでピントがでました)。

2月5日は「月面X」が見えるので帰宅後早速準備をします。ただこの冬一番の最強寒波で顔が凍りそうに冷たい!

SV230スーパーズームを20㎜(36倍)にして眺めてみると小さくきれいに「月面X」が見えていました。そこをiPhoneのカメラを使って手持ちコリメートで撮影。

ここからがこのアイピースの素晴らしいところ! アイピースを覗きながらズームリングを回していく~どんどん月が大きくなり、視野も広くなっていく。8㎜(89倍)で半月が視野一杯になり「月面X」も見やすくなってきました。

このくらいの倍率で眺める月が一番美しいと思いますが、「月面X」の部分をもっと拡大して見たくなりました。
そこで登場するのがSV215 3㎜~8㎜プラネタリーズームアイピースです。このアイピースで3㎜(238倍)で眺めると「月面X」もこんなに大きくはっきりと見えてしまいます。
ただし、2インチの天頂ミラーを使うとこの望遠鏡ではピントが出ませんでしたので、アメリカンサイズの正立プリズムを使いました。

下が2インチ天頂ミラーとSV230スーパーズーム、上がアメリカンサイズ正立天頂プリズムとSV215プラネタリーズームです。

SV215 プラネタリーズームは以前にナグラーズームと比べた記事が過去にありますので、よろしければご笑覧ください。
そして第1報の時のようにSV230スーパーズームに一眼レフカメラを接続し、「月面X」を撮ってみました。この場合は50㎜程の延長筒が必要でした。
風が強くてZERO経緯台ではさすがに辛いのでアトラクス赤道儀に載せ替えました。

まずは20㎜で~

ズームリングを回して8㎜にしました。眼視ではピントのズレはほとんど感じませんがカメラを付けてズームするとやはりピントはかなりズレます。ピントを合わせなおして撮影。

なんだか一眼レフで撮るよりiPhone手持ちコリメートの方がきれいに撮れている気がしますがどうなんでしょうね~。きっとiPhoneに搭載されているカメラの性能がかなり素晴らしいのでしょう!
初心者の方がこれからガッツリ月や惑星、星雲・星団などを今回私が使った10㎝屈折望遠鏡で見ようとするのであれば、このSV230スーパーズームが1本あればかなり楽しめるのではないかと思います。そしてもっと高倍率で見たくなった時にSV215プラネタリーズームを追加するというのも良い選択肢ではないかと思います。
SV230スーパーズーム、SV215プラネタリ―ズーム、SV503 102EDと使いましたが、どれもコストパフォーマンスの良い素晴らしい製品で、これから望遠鏡を買って星を見ようとする方にはお勧めしたい機材です。
ただし、鏡筒はファインダーやファインダー台座、天頂プリズムなどは別売りなので注意が必要です。









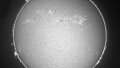





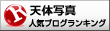
コメント